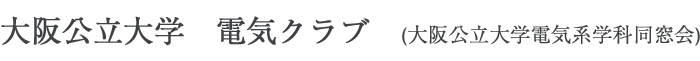学生コラム
学生コラム
2024年3月21日
第5回
大阪府立大学 工学部 電子物理工学課程
北村暖心
北村暖心
私の研究室ではキラリティにまつわる研究を行っている。キラリティとは、ある物質とその鏡像異性体が重なり合わない関係性のことであり、19世紀後半にLord Kelvinにより定義された。例えば、螺旋階段やDNAの構造を思い浮かべれば理解できる。興味深いことに、彼による定義のおよそ100年前、Goetheは一部の花の形状やツタの巻き方が螺旋であることに気づき、自然界のらせん秩序であると言及した。そして彼に続き、現在のキラリティ研究にも通ずるような研究が、科学が発展途上の段階にもかかわらず積み上げられていった。彼らの鋭き科学的洞察は、如何なる思想のもとで養われたのだろうか。
専門分野を用いて論じても複雑化するだけなので、簡単な思考実験を行ってみる。科学の考え方に則り、“科学を考える我々自身”に対し必要最小限の要素以外をすべて排してみよう。そうすると、古典物理で物体を質点とみなすように、我々は思考する球体とみなすことができる。この場合、如何にして“左右”の概念を区別することができるだろうか。2つの互いに相異なる存在、例えば腕や足が2本ずつあれば容易であっただろう。ここで、日常における認識能力は自身の有する身体的特徴に依存することに気づかされる。ならば、外的環境により方向を定義するほかないだろう。しかし、ある朝突然世界の“左右”が反転してしまったとしたら、その異常に気付くことはできるのだろうか。
デカルトによれば、あらゆる疑しさを排してゆけば自身の精神が残り、思考に先立つ“自分自身”という存在の必要性が生じると説いた。左右の概念を論じるには、球体としての近似ではなく、これまで生きてきた我々自身の存在がなければならないのだろう。それでは、特定の植物が好んで左巻きの模様を現わしたり、右巻きにツタをのばしたりするのは、彼ら自身が左右を区別しているからなのだろうか。
Goetheがこのような与太話に思いを馳せていたかどうかは知る由もないが、思考の主たる存在の必要性に辿り着いたとき、それが嗜好性を持つ余地を残すと考えたのではないだろうか。だからこそ、同種ならほぼ同じ向きを好む植物に違和感を抱いたのではないか。我々の行使する科学も、外積だとか右ねじの方向だとか、昔の誰かの好みによって整列させられている部分が多く、ヒトも植物も等しく奇妙で謎多き存在である。
以上の浅学なお話に、有識者たる読者諸君は数多の疑問を抱いたはずである。下らない疑問の一つ一つに回答を付さんとする好奇心が沸いたなら、誰しもが過去の偉人たちと同じように、科学を紡いでいく先駆者となりえるだろう。